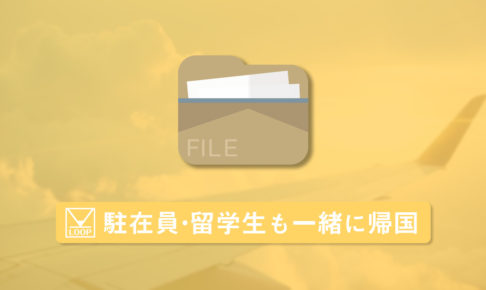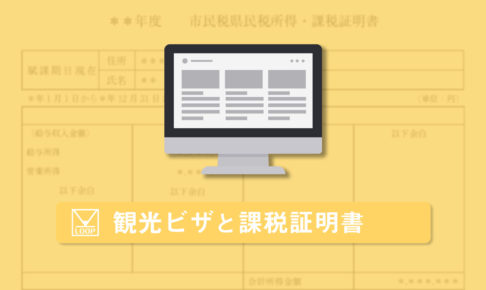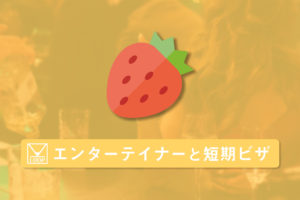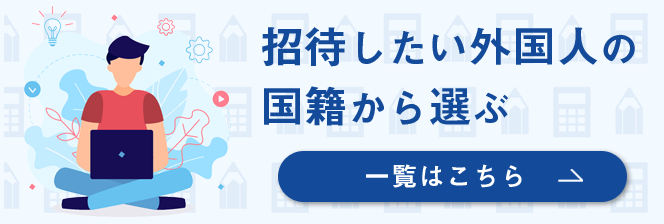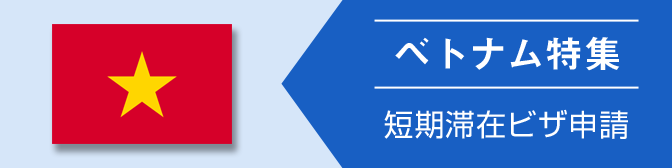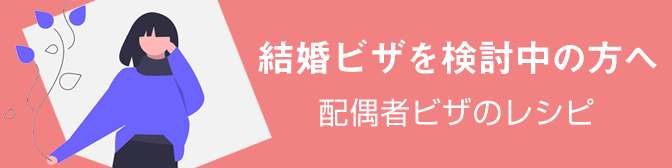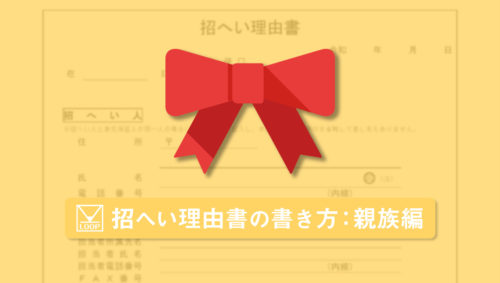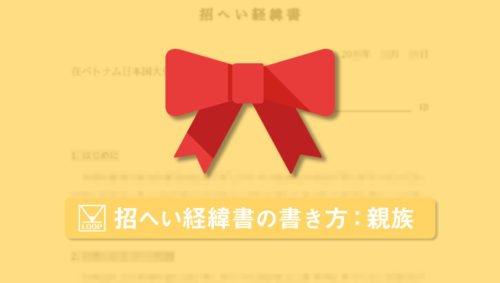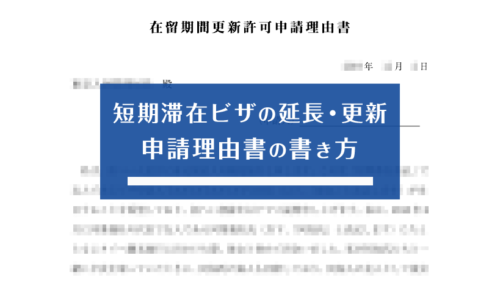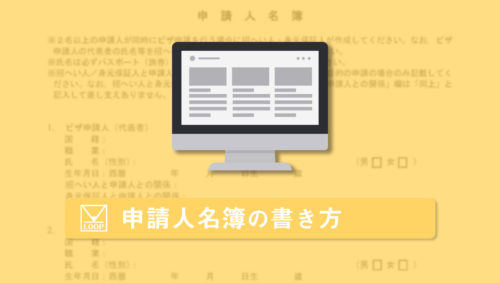海外で暮らす恋人や友人、親族を短期間(90日間以内で)日本へ招待するには、短期滞在ビザという査証を現地の大使館や総領事館へ申請しなければなりません。
そして、日本側で書類を準備して申請する場合、協力者となる招へい人(招待する人)・身元保証人はそれぞれ日本で暮らしていることが大前提となります。
この記事では、海外駐在・赴任経験者の短期ビザ申請をテーマに解説しています。
この記事の目次

駐在・赴任経験者の注意点
結論から話すと、最近まで駐在・赴任していた方は、申請時に求められる書類が揃いにくいというデメリットがあります。
- 海外赴任のため数ヵ月前に帰国したばかり
- 出張のため一時的に住民票を抜いていた
- 最近まで海外へ留学していた
上記のようなケースでは、必要書類が揃わないことも珍しくなく、通常の申請では提出しない特別な補足資料を添付・作成する機会が多くあります。
そして、その必要書類とは、ほとんどのケースで課税証明書を指します。
課税証明書の取り扱い
前述のとおり、課税証明書は年収を証明する資料で、お住まいの市/区役所から発行されます。
“1月1日時点”がポイント
しかし、発行にはひとつ条件があり、その年の1月1日からその地域で暮らしている、すなわち1月1日時点で住民票を置いていることが求められます。
日本国内の企業に在籍し、日本国内で長年暮らしている人にとっては何の障壁にもなりませんが、海外に赴任していた方にとってはやっかいな問題になります。
なぜなら、ある市区町村から別の地域へ引っ越した場合は、以前居住していた地域の市役所・区役所へ請求すれば課税証明書が取得できます。一方で、海外赴任を終えその年の1月1日以降に帰国した場合、以前暮らしていた地域は海外になります。
つまり、請求先となる市役所・区役所が存在せず、結果的に課税証明書自体が発行されません。

1月1日以前の帰国も要注意
その年の1月1日以前に帰国して住民票を置いた場合のみ、当年度の課税証明書が発行されることは理解できたかと思います。しかし、取得してそのまま添付するだけでは不十分といえます。
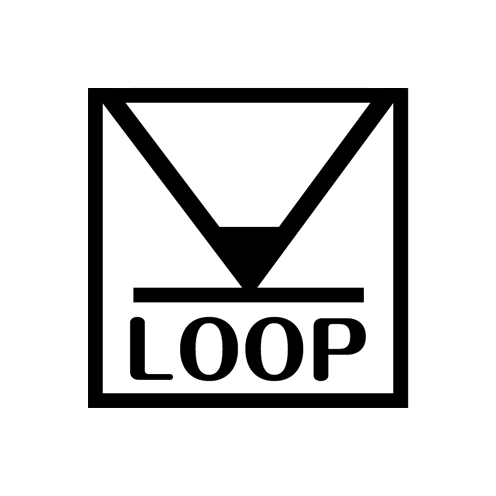
ケーススタディ
「前年の10月」に帰国して住民票を置き直し、「翌年の7月」に短期滞在ビザを申請するケースを考えてみます。

この場合、1月1日時点で住民票を日本に置いているため、課税証明書自体は発行されます。
しかし、課税証明書は、発行を受けた年の前年分の総所得が記載されるので、前年の1月分から12月分の給与1を合計した額が計上されることになります。
今回挙げた例では、「前年の10月」に帰国しているため、実質は「10月分から12月分」までの収入のみを証明することとなり、記載される年収額が低くなってしまいます。

このように、都合の良いように考えてくれるとは限らないので、積極的にこちらからアピールするべきです。
以上の理由から、実際は1月1日以前・以後の帰国にかかわらず、駐在経験者が短期ビザを申請するケースでは、通常に比べて難易度が高くなる傾向にあります。
駐在経験者が用意するべき資料
審査を有利に進めるには以下の手立てが考えられます。
直近の収入証明資料を添付
課税証明書で十分なアピールができなければ、それに代わる資料を追加するしか方法はありません。これが冒頭に説明した特別な補足資料に相当します。
- 勤務先発行の給与明細書コピー
- 金融機関発行の残高証明書
例を挙げると、上記の資料を別途準備します。
ただ、給与明細書はあくまでも民間の企業が発行するものなので、市役所や区役所、銀行などが発行する証明書に比べて書類の信用力が低くなります。
そのため、ほとんどの日本大使館・総領事館で、給与明細書は収入状況を証明できる資料として扱われていません。つまり、そのまま提出すると受理されない可能性があります。

現地の窓口で断られないためにも、実際は給与明細書のほかに、補足説明書2と呼ばれる書面を作成・添付するのが一般的です。
給与明細書と補足説明書
給与明細書を添付する場合は、以下のような項目を書面に組み込みます。
- 提出できない旨を明記する
- その上でなぜ提出できないかの理由
- 代わりにどんな書類を提出するか
- その書類は何を証明しているものか
イレギュラーな資料を添付する場合は、審査官に意図が伝わるよう、こちらから説明を加えることが不可欠です。
まとめ
- 課税証明書が発行されるかを確認
- 代替資料(残高証明・給与明細など)の検討
- 給与明細提出時は別途説明書を作成
課税証明書が提出できない、または給与の全額が反映されていない時点で特殊な申請になるため、補足資料の検討は非常に大切です。
帰国後数年が経過していれば、通常の添付資料のみで審査は進んでいきますが、帰国後すぐに申請する場合は、こういった細かいことにも気を配る必要があります。